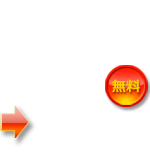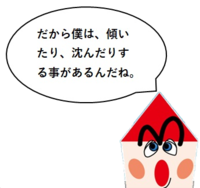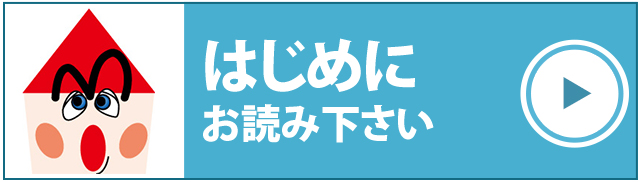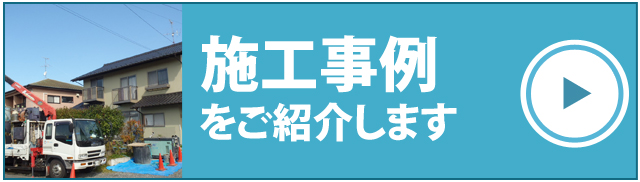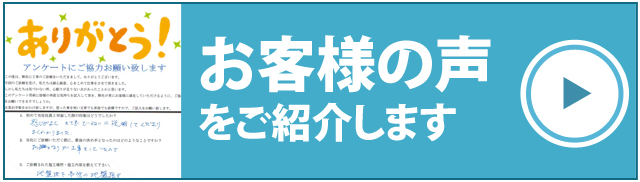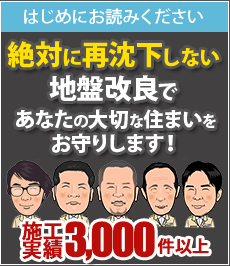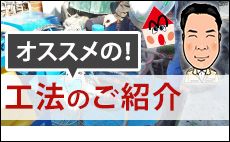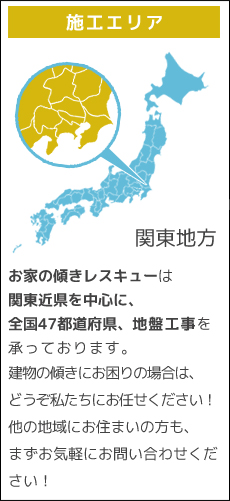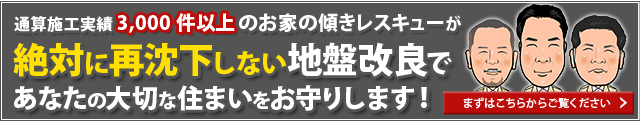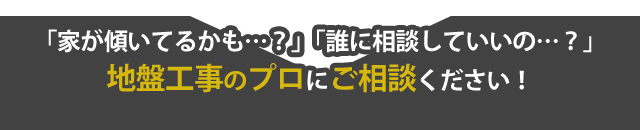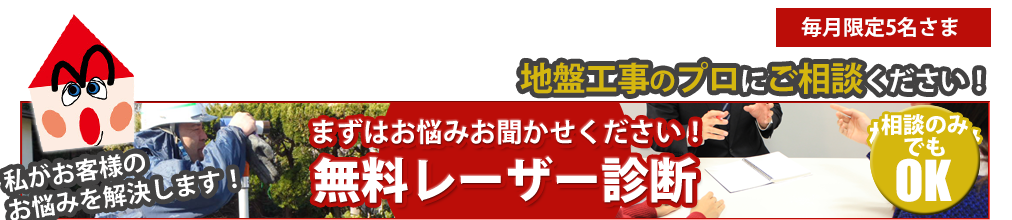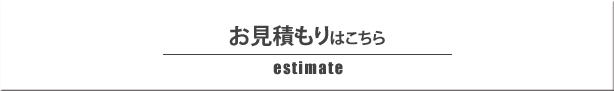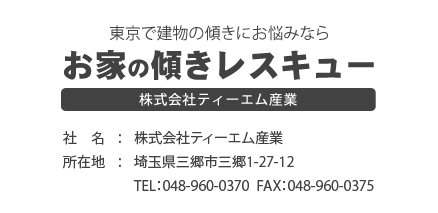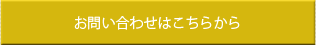地盤について知ろう 最終回 局所的地盤沈下
|
< 地盤について知ろう 最終回> お家の傾きレスキュー
局所的地盤沈下近隣の工事が原因で発生したり、盛土(もりど)や埋戻し土の軟弱な地盤に耐力を超える荷重が乗ってしまったことで起こります。 盛土(もりど)元々ある土地に土を盛る事です。勾配を作りたい・なくしたい時に行います。盛土は、その名の通り「土を盛っている」ということで、盛った段階で土を締固めで強度を上げますが、適切な締固めが出来ていなければ、基礎として使用するにはあまり望ましいとは言えません。 盛土を使用する時 ・土地の勾配をなくしたい ・土地に勾配をつけたい ・圧密沈下する地盤を一定の高さにしたい ・有害物質の密封 盛土の種類 ・山砂 ・根切り土の中の良質土 ・他現場の建設発生土の中の良質土 ・再生コンクリート砂 埋戻し土埋戻しとは、基礎又は地下を造るために掘削した空間を、土で埋めることです。掘り起こした土で再度埋めていくという感じです。 埋戻し土は基本的に良質な土の利用が原則ですが、発生土・汚染土や粘土質を使用する場合もあります。埋戻し土も盛土(もりど)同様で締固めを行いますが、適切な締固めがされていなければ強度はあまり強いとは言えない地盤です。 圧密沈下土に含まれている水が時間とともに抜けていくことで、土の体積が収縮していき沈下する現象です。土の中の水を間隙水(かんげきすい)といい、土粒子(土そのものの粒)と土粒子の間の水(間隙水)がなくなっていきます。この圧密現象は、不同沈下という「どちらか一方に沈下してしまう」家が傾く原因に多い沈下を発生させます。 対策みなさん気になる事の一つとして地盤の対策ができるのかが気になるところでしょう。私達個人で対策をするという場合には、業者選びと事前にどのような地盤なのかを知るということです。どのような地盤か個人で知っておくは非常に重要ですが、今現在では住宅品質確保促進法がありますので安心して良いのではないかと思います。 |
家の傾きを直す工事
- 投稿日:2019年 6月 5日
- テーマ:その他
ホームページの施工事例の方でも作業手順はある程度把握できると思いますが、ブログの方でわかりやすく作業手順をご紹介させて頂きます。
家の傾き工事 <挨拶回り>
まずはじめに、工事日が確定後、工事開始前までに近隣の方々に挨拶を行います。「作業音がうるさいなどがありましたら弊社までご連絡下さい」などという文章を添えた紙をとともに全力で伺います。
家の傾き工事 <施工前>
工事当日にA様邸(仮名)へ伺い、そこで写真を撮影します。
このように施工場所などの写真を撮影します。 ※他にも各場所の写真を何枚か撮影します。
撮影後は工事で使う道具などを準備します。
家の傾き工事 <掘削>
ある程度の準備が完了したところで、人力掘削(穴掘り)作業に入ります。
機械などではなく、人の手で穴を掘っていきます。

写真のように人が入れるスペースの穴を掘ります。工事場所によっては左右に壁などがあり、横のスペースを広げる事が出来ない場合は縦に少し掘ったり、またはその穴に入れる人員を選択することもあります。
ちなみに中の写真はこのような感じになっています。このスペースの中で次に行うジャッキを設置していきます。

家の傾き工事 <ジャッキ設置>
人力掘削作業が終了したところで、ジャッキの設置を行います。
ジャッキを設置する前に杭というものを地面に打ち込みます。地盤の固い部分である支持層というところに到達するまで何個も打ち込んでいきます。到達を確認したところでジャッキを設置していきます。
家の傾き工事 <ジャッキアップ>
各ポイントにジャッキの設置が完了したところで、ジャッキで家を持ち上げる作業に移ります。持ち上げ作業も手動で行います。設置したジャッキに操作レバーを取り付け、各自、各ポイントに潜りこんで、合図する人の掛け声で同時に持ち上げます。家の傾き工事 <束調整>
ジャッキで家を持ち上げた際に束と束石の間に隙間が空くのでその部分を調整していきます。
写真は調整した後になります。このような感じですべての束と束石の隙間を整えていきます。
家の傾き工事 <充填注入>
いよいよ家の傾き工事も終盤を迎えていきます。充填注入では、ジャッキで持ち上げた際にできる隙間を注入作業で埋めていきます。A液(セメント)とB液(珪酸)を同時に地面へとおくっていきます。ちなみにB液(珪酸)は使用しない場合もあります。

家の傾き工事 <施工完了>
施工前とあまり変わらない状態にまで仕上げて作業完了です。
一通り工事の流れをご紹介致しました。他の業者さんと作業内容は多少違う部分はあると思いますので、参考程度に受け取ってください。
地盤について知ろう 第二回 地盤が起こす現象
|
< 地盤について知ろう 第二回> お家の傾きレスキュー |


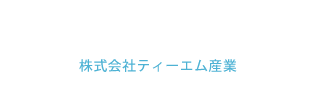
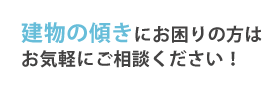
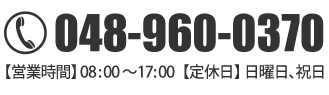
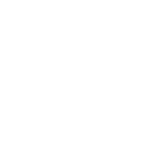
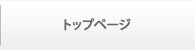
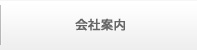
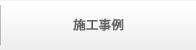
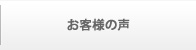

 048-960-0370
048-960-0370 電話で見積り・相談
電話で見積り・相談